こんにちは、そうま灯火です。
会社員の場合、入社時に財形貯蓄を始めた人が多いのではないでしょうか。
当時は有利かと思って始めたことも、省みると他により良い選択肢があるかもしれません。
結果として、財形貯蓄は解約してiDecoに切り替えました。
なんとなく入社以来給与天引きで積み立てしている財形貯蓄があれば、下記の状況に当てはまる場合、解約検討の余地があります。
- 財形住宅貯蓄をしているがマイホーム購入予定がない
- iDecoに加入可能で拠出限度額と財形貯蓄の積立金額が近い
- iDecoに加入可能で財形年金貯蓄に加入している

財形貯蓄は会社員の場合、入社時に福利厚生の一環で募集されていますが、本当に自身の資産形成の方針に即したものなのでしょうか。
同じような非課税制度として、NISAやiDecoが注目されています。
財形貯蓄との違いは何なのでしょうか、徹底解説します!
資産形成オススメリンク
- 投資一般(個別株、投資信託、ETFなど)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- つみたてNISA
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- ジュニアNISA ※2023年に廃止
- 積立保険(学資保険)
- 奨学金
目次
財形貯蓄とiDeCoの比較と解約した理由

結果として、財形貯蓄は解約してiDecoを始めました。
判断するためには財形貯蓄とiDecoの性質をよく理解して、自身に即しているかを知る必要があります。
財形貯蓄と自身の積み立て状況について
まずは財形貯蓄についておさらいしてみましょう。
財形貯蓄とは
財形貯蓄は厚生労働省のWEBページにて確認することができますが、大まかなポイントをまとめますと以下の通りです。
- 財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類ある。
- 勤務先が福利厚生の一環として準備しており、勤務先へ申請することで加入できる。
- メリットは種類によって異なるが、共通しているのは給与天引きで積み立てられることと利息(預金金利)に対して非課税であることである
自身の積み立て状況
財形貯蓄は入社時の応募より加入しており、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄で合計10,000円を毎月積み立て(解約時で概ね100万円の積立)ていました。
財形貯蓄に加入した理由は3つありました。
- 給与天引きで積み立てできることで、強制的に貯蓄できると思ったから。
- 財形住宅貯蓄については、財形持家融資ができることを知っていたから。
- 周りがやっていたから。親に勧められたから。
iDeCo(個人型確定拠出年金)について
iDeCo(個人型確定拠出年金)は厚生労働省のWEBページで確認できます。
ポイントは以下の通りで、ちなみに私の場合は「加入可能・掛金上限は12,000円/月」でした。
- 毎月定額を積み立て(拠出)して投資信託などに投資できる。
- 優遇税制が適用されることで節税メリットがある。具体的には、掛金に対する所得控除と運用利益については非課税となる。
- 加入の可否および積み立て金額の条件(拠出限度額)は、職業などにより異なる。
財形貯蓄を解約してiDeCoに切り替えた理由
財形貯蓄をおさらいして、iDecoについて制度を確認したところ、以下の条件から財形貯蓄を解約することにしました。
- 超低金利時代が継続されており銀行預金ではなく投資が必要と思うようになったから。
- 妻(結婚相手)と私にマイホーム願望がなかったから。
- iDeCo制度および自身の加入条件について知り、資産形成のポリシーに即しており、かつ無理なく移行できると判断したから。
1つ目は、2012年の加入時から銀行は低金利(低利息)でしたが、2023年現在継続しており資産は預金で増やす時代ではないと感じるようになったからです。
親の世代は銀行定期預金の利息が約6%の世代ですので、預金しておくだけで資金はぐんぐん増えていきました。
しかしながら、今の時代はそうではありません。
大手メガバンクだと預金利息は0.001%であり資産の増加は見込めません。
2つ目は、妻と私にマイホーム願望がなかったからです。
財形貯蓄加入理由として、財形持家融資の存在がありました。
財形持家融資とは、簡単に言えば財形住宅貯蓄を一定期間・金額を続けたら、優遇金利で住宅購入の融資を受けることができるという制度です。
財形住宅貯蓄を続けても、住宅を建てるライフプランじゃないのであれば、加入する理由はありません。
3つ目はiDeCoについて知ったことです。
iDeco制度は自分には関係ないと思っていたのですが、改めて確認したところ自身もiDeCoに加入することができることがわかりました。
しかも、自身の場合は掛金が上限12,000円/月ということもあり、財形貯蓄の積立金額と近いため家計に踏み込んだ見直し必要ありませんでした。
財形貯蓄の途中解約とiDeCoのデメリット

財形貯蓄を解約することと、iDeCoに切り替えることのデメリットについても理解しておきましょう。
財形貯蓄で非課税だった利息は5年に遡って課税(遡及課税)される
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、それぞれ引き出しの用途が年金と住宅購入費に限定されるため、途中解約は目的外払い出しに該当します。
よって過去5年間に遡り、非課税だった利息に改めて課税されます。
例えば、積立額100万円の場合、利息は0.001%として10円。そのうち非課税として恩恵を受けていたのは2円です。
正直、痛くも痒くもありません。銀行預金はナンセンスと感じてしまいますね。
財形貯蓄よりiDeCoの方が資金拘束力が強い
iDeCoのデメリットとして資金拘束力が強いことがあげられます。
iDecoは、ほとんどの場合において一度始めたら60歳まで引き出すことはできません。
今回のような途中止めは認められていないということですね。
それでも節税の観点でいえば大変効果がありそうなので、iDeCoの申込をしました。
申込におけるプロセスと商品や掛金の配分については別記事にてご確認ください。
iDeco申込のプロセスと開設後について徹底解説!
まとめ
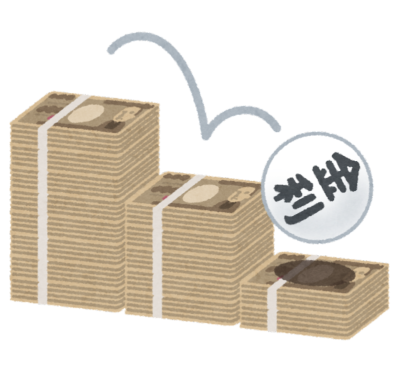
本記事では、財形貯蓄とiDeCoについて比較して、財形貯蓄を解約してiDeCoで積み立てすることを判断した理由について解説しました。
- 財形住宅貯蓄をしているがマイホーム購入予定がない
- iDecoに加入可能で拠出限度額と財形貯蓄の積立金額が近い
- iDecoに加入可能で財形年金貯蓄に加入している

入社したときになんとなく加入していた財形貯蓄があれば見直しましょう。
やっぱり財形貯蓄の方があってる!という場合も、現状を再認識する良い機会となりますよ。
以上、そうま灯火でした。
最後までご覧いただきありがとうございました。


